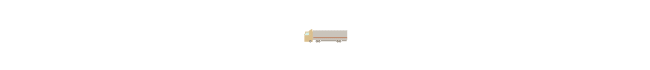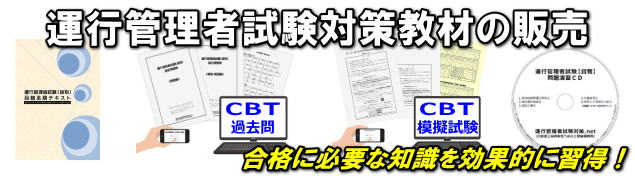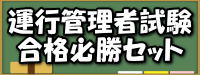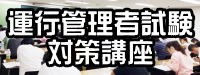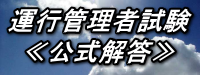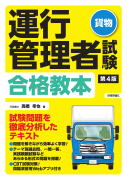法改正情報
※運行管理者試験では、法令等の改正があった場合、「改正された法令等の施行後6ヵ月間は改正前と改正後で解答が異なることとなる問題は出題しない」とされています。(試験センターWebサイトより)
ただし、令和6年4月1日に改正規定が施行された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)は、例外的に令和6年度第1回試験(令和6年8月試験)の出題対象となりました。
- R7.08.07:業務前自動点呼の運用開始に伴う関連通達の改正について
- R7.06.01:拘禁刑の創設について
- R7.04.30:業務前自動点呼の運用開始について
- R7.04.01:車検の受検可能期間の拡大について
- R7.04.01:荷待時間や荷役作業・附帯業務の「業務記録」への記録義務の対象拡大について
- R7.04.01:貨物自動車運送事業法の改正について
- R6.04.01:労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の改正について
- R6.04.01:遠隔点呼等を実施することが可能な場所の拡大等について
- R6.04.01:中間点呼における遠隔点呼等の導入について
- R6.04.01:改善基準告示の改正に伴う関連告示の一部改正について
- R6.04.01:大型トラック等の高速道路における最高速度の引き上げについて
- R6.04.01:運賃及び料金、運送約款等のウェブサイトへの掲載について
- R5.07.01:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
- R5.04.01:遠隔点呼・業務後自動点呼・特定自動運行貨物運送等について
- R5.04.01:特定自動運行に係る許可制度の創設等について
- R5.01.04:乗務後自動点呼の運用開始について
- R5.01.01:自動車検査証の電子化(ICカード化)について
令和7年6月1日
点呼告示の改正により業務前自動点呼が運用開始されたことに伴い、関連通達(貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について)が改正されました(施行:令和7年8月7日)
令和7年6月1日
懲役及び禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されました。これにより、従来「懲役」や「禁固」と規定されていた罰則規定は、すべて「拘禁刑」になりました。(施行:令和7年6月1日)
参考資料:拘禁刑の創設について(R7.6.1)
令和7年4月30日
「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」(点呼告示)が改正され、業務前の自動点呼が制度化されました。(施行:令和7年4月30日)
令和7年4月1日
道路運送法施行規則の一部改正により、車検を有効期間そのままで受けられる期間が、車検証の有効期間満了日の「1ヵ月前」から「2ヵ月前」に拡大されました。(施行:令和7年4月1日)
令和7年4月1日
貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正により、業務記録における荷待時間・ 荷役作業等の記録義務の対象となる車両が、「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の車両」から「全車両」に拡大されました。(施行:令和7年4月1日)
令和7年4月1日
貨物自動車運送事業法の一部改正により、「1.運送契約締結時等の書面交付義務」、「2.委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務」、「3.実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務」などについて規定されました。(施行:令和7年4月1日)
令和6年4月1日
令和4年12月に公布された労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の改正規定が施行されました。これによりトラック運転者の拘束時間・休息期間・連続運転時間のルールが大幅に変更されました。(施行:令和6年4月1日)
参考資料1:改善基準告示の改正について(R6.4.1) 参考資料2:労働時間等の改善基準のポイント
令和6年4月1日
点呼告示(対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示)の一部改正により、遠隔点呼等を実施することが可能な場所として、運転者等が従事する運行の業務に係る自動車の車内、宿泊施設や待合所等も認められました。また、使用機器に関する規定も一部改正されました。(施行:令和6年4月1日)
令和6年4月1日
貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正により、中間点呼の実施方法について、対面点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(遠隔点呼等)も可能となりました。(施行:令和6年4月1日)
令和6年4月1日
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の改正に伴い、関連告示の規定が一部改正されました。(施行:令和6年4月1日)
令和6年4月1日
道路交通法施行令の一部改正により、車両総重量8トン以上の中型・大型トラックの高速自動車国道における最高速度が90㎞に引き上げられました。(施行:令和6年4月1日)
令和6年4月1日
貨物自動車運送事業法の一部改正により、一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款など所定の事項について、ウェブサイトへの掲載により公衆の閲覧に供することとされました。(施行:令和6年4月1日)
令和5年7月1日
道路交通法の一部改正により、車体の大きさや構造等が一定の基準に該当する原動機付自転車が「特定小型原動機付自転車」とされ、交通方法等に関する規定が整備されました。いわゆる電動キックボードなどが特定小型原動機付自転車に該当します。(施行:令和5年7月1日)
令和5年4月1日
貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(点呼告示)の制定により、遠隔点呼・業務後自動点呼が実施できるようになりました。また、自動車運送事業者等が自動運転車を用いて事業を行う場合の規定が整備されました。(施行:令和5年4月1日)
令和5年4月1日
道路交通法の一部改正により、自動運転レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行おうとする者についての許可制度の創設や一部の用語の定義などが変更されました。また、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務とされました。(施行:令和5年4月1日)
令和5年1月4日
点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度が創設され、乗務を終了した運転者に対する点呼を自動で行うことができるようなりました。(令和5年1月より運用開始)
令和5年1月1日
道路運送車両法の一部改正により、自動車検査証(車検証)が電子化(ICカード化)されました。(施行:令和5年1月1日)
令和4年5月13日
道路交通法施行令の一部改正により、自動車の積載物の積載制限が一部緩和されました。また、道路交通法の一部改正により大型・中型免許取得の受験資格が一部緩和されました。(施行:令和4年5月13日)
高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定の整備について
道路交通法の一部改正により、75歳以上で過去3年間に信号無視などの一定の違反歴がある方は、免許証更新時に運転技能検査の受検が義務化されました。また、所定の安全運転支援装置を備えた安全な車のみ運転を継続できる「サポートカー限定免許」の申請が可能になりました。(施行:令和4年5月13日)
令和4年4月1日
実施要領で定める要件を満たす機器・システムを用いて遠隔拠点間で行う「遠隔点呼」の運用が開始されました。(令和4年4月1日より運用開始)
令和3年1月26日
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(通達)の一部改正により、摩耗した冬用タイヤの雪道での使用の抑止についての規定が盛り込まれました。(施行:令和3年1月26日)
令和2年12月1日
令和2年6月10日に交付された改正道路交通法のうち、公布の日から6ヵ月以内の施行予定とされていた「普通自転車の定義に係る規定の見直し」、「駐車、停車等に関する規定の整備」、「初心運転者標識に係る規定の見直し」についての規定が施行されました。(公布:令和2年6月10日 施行:令和2年12月1日)
令和2年6月30日
道路交通法の一部改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設され、さらに免許の取消処分の対象に追加されました。(公布:令和2年6月10日 施行:令和2年6月30日)
※同日付けで、「普通自転車の定義に係る規定の見直し」、「駐車、停車等に関する規定の整備」、「初心運転者標識に係る規定の見直し」に関する改正条文も公布されましたが、これらの規定については公布の日から6ヵ月以内の施行とされており、令和2年12月1日に施行されました。
※同日付けで、「高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定の整備」、「第二種免許等の受験資格の見直し」に関する改正条文も公布されましたが、これらの規定については公布の日から2年以内の施行とされており、令和4年5月13日に施行されました。
令和2年4月1日
労働基準法が一部改正され、賃金台帳等の記録の保存期間が5年間に延長されました。(施行:令和2年4月1日)ただし、経過措置により、当分の間は3年間となります。
令和2年4月1日
道路交通法施行令が一部改正され、自動車が高速自動車国道の本線車道に接する加速車線又は減速車線を通行する場合の最高速度が本線車道を通行する場合と同一となりました。(施行:令和2年4月1日)
令和元年12月1日
道路交通法が一部改正され、携帯電話使用等に関する罰則が強化されるとともに、同違反に係る基礎点数および反則金の額が引き上げられました。その他一部の交通用語や免許の仮停止処分に関する規定が改正されました(施行:令和元年12月1日)
令和元年11月1日
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、「規制の適正化」、「事業者が遵守すべき事項の明確化」に関する規定が施行されました。 (施行:令和元年11月1日)
令和元年7月1日
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、「荷主対策の深度化」に関する規定が施行されました。(施行:令和元年7月1日)
参考資料:荷主対策の深度化について(R1.7.1)
令和元年6月15日
貨物自動車運送事業輸送安全規則が一部改正され、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合において、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合は、当該作業等の内容を乗務記録に記録することとなりました。(施行:令和元年6月15日)
平成31年4月1日
平成30年12月14日
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部が改正され、大雪時の道路交通の確保のため、いわゆるチェーン規制が実施されることとなりました。(施行:平成30年12月14日)
平成30年10月1日
自動車点検基準が一部改正され、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の大型自動車のスペアタイヤについて3ヵ月ごとの点検が義務付けられました。(施行:平成30年10月1日)
平成30年6月1日
貨物自動車運送事業輸送安全規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(通達)の一部改正により、睡眠不足の乗務員を乗務させてはならないこと等が明確化され、点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況が追加されました。(施行:平成30年6月1日)
平成30年4月1日
貨物自動車運送事業輸送安全規則が一部改正され、安全管理規程の設定等の義務付けの対象となる事業者について、従来、事業用自動車を「300両以上」所有している事業者だったものが、「200両以上」に拡大されました。(施行:平成30年4月1日)
平成30年3月30日
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(通達)が一部改正され、過労運転の防止策については自動車運送事業主や事業者役員等が運転者を兼ねる場合にも適用されること。また、「車庫と車庫間」によるIT点呼の実施が可能になりました。(施行:平成30年3月30日)
平成29年9月29日
貨物自動車運送事業者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可を受けている場合であって、一般貨物自動車運送事業等と旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運行を管理する営業所が同一敷地内にある場合、貨物自動車運送事業及び旅客自動車運送事業に係る運行管理者資格者証を併せて有する運行管理者は、旅客自動車運送事業の当該営業所の運行管理者又は補助者を兼務することが可能となりました。(施行:平成29年9月29日)
平成29年9月1日
旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の両事業の許可をそれぞれ取得した場合には、乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、一定の条件のもとで事業の「かけもち」を行うことができるようになりました。(施行:平成29年9月1日)
平成29年7月1日
トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るため、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等が乗務記録の記載対象として追加されました。(施行:平成29年7月1日)
平成29年3月12日
準中型免許創設に伴い、トラックの初任運転者等について安全運転の実技を義務化する等、運転者教育の強化を図るため、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部が改正されました。(施行:平成29年3月12日)
平成29年3月12日
貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」が新設されました。(施行:平成29年3月12日)
平成29年1月16日
道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行され、自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転を防止するために必要な医学的見地に基づく措置を講じなければならないこととされました。(施行:平成29年1月16日)
平成29年1月1日
道路運送車両法施行規則等が一部改正され、図柄入りナンバープレートの導入、検査標章のデザイン変更等が行われました。これにより、今後、ナンバープレートの多角的な活用や、検査標章の見やすさ向上による無車検運行の防止等が推進されます。 (施行:平成29年1月1日)
平成28年7月1日
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(通達)が一部改正され、「(1)同一事業者内における遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者によるIT点呼の実施(Gマーク営業所に限る)」、「(2)一定の条件を満たす場合において、Gマーク未取得営業所でのIT点呼の実施」、「(3)酒気帯び状況の測定結果のクラウド型機器による記録保存」が可能となりました。(施行:平成28年7月1日)
平成28年6月18日
道路運送車両の保安基準の改正により、後写鏡(バックミラー)等の代わりに、 後方確認装置(カメラモニタリングシステム)を使用することが可能となりました。 (施行:平成28年6月18日)
平成28年4月1日
道路運送車両法、道路運送車両法施行規則の改正及び所要の告示の整備により、ナンバープレートの表示義務が明確化され、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されました。
また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなります。(施行:平成28年4月1日)
平成27年9月1日
トラック運転者のフェリー乗船時間を原則として休息期間として取り扱うものとし、通達の一部が改正されました。(施行:平成27年9月1日)
平成27年6月17日
酒気帯び運転や過労運転等で交通事故を起こして人を傷つけた場合も、運転免許の仮停止の対象となりました(道交法103条の2参照)。(公布:平成27年6月17日 施行:平成27年6月17日)
平成27年5月18日
自動車事故報告書等の取扱要領が改正され、「脳疾患、心臓疾患及び意識喪失」に起因すると思われる事故が発生した場合には、自動車事故報告規則第4条第1項の規定に準じ、速報することとされました。(施行:平成27年5月18日)
平成26年12月1日
貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、貨物自動車運送事業者等の遵守事項として、道路法第47条の規定等に違反する事業用自動車による運行の防止について、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならないこと等を新たに追加することとなりました。(公布:平成26年12月1日 施行:平成27年1月1日)
運行記録計の装着義務付け対象の拡大について
貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大されることとなりました。(公布:平成26年12月1日 施行:新車は平成27年4月1日、その他の車両は平成29年4月1日)
平成26年1月22日
貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、「適正な取引の確保」に関する条文が新たに追加されました。(公布:平成26年1月22日 施行:平成26年4月1日)
平成25年7月30日
トラック事業における輸送の安全の確保及び経営環境の改善のため、共同点呼(受委託点呼)制度が導入されます。(施行:平成25年11月1日)
平成25年3月29日
貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、特殊な輸送等の場合を除き、全てのトラック事業者の営業所において、運行管理者を選任することを義務付けることとされました。(公布:平成25年3月29日 施行:平成25年5月1日)
平成23年3月31日
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部を改正し、Gマーク認定事業所に対するインセンティブとしてのIT点呼の実施に係る要件が拡大されることとなりました。(施行:平成23年4月1日)
平成23年3月25日
東北地方太平洋沖地震によるアルコール検知器の生産・出荷への影響を 踏まえ、自動車運送事業者の点呼における運転者の酒気帯びの確認のため のアルコール検知器使用の義務化の実施時期が4月1日から5月1日に延期されました。
平成22年4月28日
事業用自動車の飲酒運転ゼロの目標を達成するため、点呼時にアルコール検知器の使用を義務付ける等の改正が行われます。(公布:平成22年4月28日 施行:平成22年4月28日及び平成23年4月1日)
平成21年11月20日
自動車運送事業者等が引き起こした社会的影響が大きい事故の速報に関する告示が制定されました。(施行:平成21年12月1日)